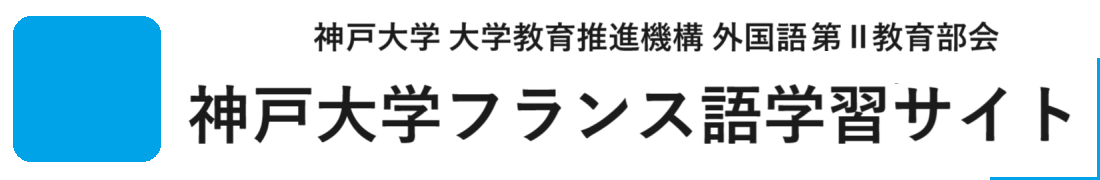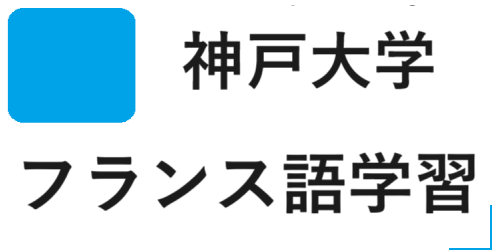ごあいさつ
第二外国語としてのフランス語とは?

皆さんにとってはおそらく、高校まで外国語といえば英語オンリーだったのではないかと思います。
神戸大学では入学時に、ドイツ語・フランス語・中国語・ロシア語の4言語の中から一つを選び、一年間をかけて、自分の好きな外国語を勉強することができます!(裏を返せば、どれか一つ勉強しなくちゃいけません・・・)
これからの時代を生き抜いていくため、さらにはリーダーとして世の中を動かして行くためには、コミュニケーション・ツールとしての英語力が不可欠だと、昨今よく言われるようになりました。
とはいえ、世界には英語以外にも様々な外国語があり、それを話す多種多様な国や民族や文化が存在しています。
しかしながら、そのような多様性の存在は「英語」というツールを通してだけではなかなか見えてきません。
皆さんには、英語以外の外国語をもう一つ学ぶことで、世界の国々や国際情勢について、より広く、より深い見識を持っていただきたいと願っています。
☆ ☆ ☆
それでは、4つの第二外国語の内、どれを選べばよいのでしょうか。
ただ何となく選んでしまったのでは、一年間の勉強はなかなか大変です。
このページでは、フランス語という言語の特徴について解説していますので、第二外国語の選択にあたって参考にしていただければと思います。
国際言語としてのフランス語

21世紀の現在において、国際的な活動といえば、なんといっても英語がなくてはなりません。
英語ができれば世界中の大多数の人たちとコミュニケーションをとることができるでしょう。
とはいえ、英語さえできればそれで本当に「国際的」と言ってしまってよいのでしょうか?
☆ ☆ ☆
実は、今から半世紀ほど前までは、国際言語といえば何よりもフランス語でした。
ヨーロッパでは16世紀ごろからフランス語が外交における共通の言語として用いられてきたことから、20世紀に入ってからも、国際的な舞台での共通言語はフランス語とされていました。
しかしながら第二次大戦後は、アメリカの国力増加に伴い、国際言語ナンバー1の地位は、フランス語から英語へと移り変わっていきました。
☆ ☆ ☆
とはいえ、そのような歴史は単なる「過去の栄光」と言ってしまえば終わりではなく、現在でも国際的な舞台でのフランス語の重要性は保たれています。
具体的には、フランス語は国際連合における公用語の一つとされていますし、国連職員の作業言語として英語とフランス語が位置付けられています。
他にも、オリンピックの公用語としてフランス語と英語の2つが定められています。
2020年オリンピックの東京開催を射止めた2013年9月のIOC総会最終プレゼンテーションに置いて、高円宮妃久子殿下とアナウンサーの滝川クリステルさんは見事なフランス語を話していましたね。
アフリカでの公用語としてのフランス語

現在でもフランス語が国際的な言語であり続けているもう一つの理由に、アフリカ諸国を初めとした世界各国での公用語としてのフランス語の役割があります。
かつての帝国主義時代にとった植民地政策により、とりわけアフリカの北部やギニア湾沿いにはフランス語を公用語とする国が数多くあります。
国名を挙げると、ガボン、カメルーン、ギニア、コート・ジボワール、コンゴ、セネガル、マダガスカル、マリ、モーリシャス、ルワンダ共和国、中央アフリカ等など、その数は22ヶ国にも達します。
アフリカには、様々な民族によって形成されている国家が少なくないため、そのような国家では、異なる言葉を話す民族間で意思疎通をはかるために、かつての宗主国で合ったフランスの言語を公用語としているのです。
例えば、将来「国境なき医師団」のようなNPO団体に参加して、アフリカでの医療支援活動に従事したい、というようなことを考えたことがある人はいませんか?
その場合、そもそも国境なき医師団もフランス人により組織されたNPOですし、活動の場所となっている国の幾つかでは英語よりもフランス語の方が話されているようです。
これからの国際問題を考える上で、アフリカ諸国の成長と貧困問題の解決は重要な課題なので、フランス語を学ぶことでこの問題に向き合う第一歩となるのではないでしょうか。
芸術・文化とフランス語

そのような国際的な重要性を持ったフランス語ですが、とはいえ、やはり「フランス」と言えば「芸術の国」というイメージではないでしょうか。
もしくは「グルメの国」? 他にも、ファッションや映画や演劇やバレエ、テニスの国際大会やツール・ド・フランスや競馬など、フランスは世界的な文化発信国となっています。
ですから何か欧米文化に関する領域で、その道を究めようとか、その伝統を学ぼうと思うとどうしてもフランスを避けては通れない、ということがあります。
実際、今もフランスには、音楽・美術・料理などを勉強しに留学している日本人がたくさんいますしね。
☆ ☆ ☆
どうしてフランスが一大文化国家になったのかというと、これまたやはり深い歴史があるのです。
もともとヨーロッパの文明の起源は古代ギリシャにあると言われていますが、やがてその文明の中心は古代ローマへと移行。
その後も中世の間はイタリアがヨーロッパの文化の中心だったのですが、16世紀~19世紀の間、イタリアが国家統一することなく小さな国に分かれている間、フランスは絶対王政により強い国家を築いていました。
国家が安定して豊かだと、文化の発展にもお金をかけられるので、ヨーロッパの文化の中心は、イタリアからフランスへと移行したのです。
☆ ☆ ☆
では今はどうなのか?
昔と違って現代は文化そのものが多様化・多極化しているため、どこが中心なのかということは難しいでしょう。
とはいえ、数世紀にわたってフランスが西洋の文化の中心地であり続けたという過去は、現代に継承されている様々な文化について考える上で、重要な点だと言えるでしょう。
日本とフランス

そのようなフランス文化に日本人は深い関心を持ち、19世紀後半から現在に至るまで受容してきました。
その結果、様々なフランス語が日本語の中にカタカナ語として取り込まれています。
たとえば、ジャンル、デッサン、モチーフ、バレエ、コンクール、シェフ等などです。
とりわけフランス文学から日本芸術が受けた影響は今でも大きく、2013年に公開されたスタジオ・ジブリの宮崎駿監督『風立ちぬ』は、そもそもタイトルが20世紀初頭のフランス詩を代表するポール・ヴァレリーの詩篇『海辺の墓地』の一節「Le vent se lève, il faut tenter de vivre(風が立つ、生きねばならない)」からとられたものです。
明治から昭和にかけての小説は当然ですが、現代のクリエイターでも、フランス文学から直接的・間接的な様々な影響を受けていると言えるでしょう。
☆ ☆ ☆
しかしながら、フランスと日本の文化交流は、けっしてフランス⇒日本の一方通行ではなく、日本文化がフランス文化に対して影響を与えてきたという側面もあります。
例えば19世紀後半から20世紀初頭にかけては、開国後の日本からフランスに持ち込まれた浮世絵や陶芸品などが流行となり「ジャポニスム」としてもてはやされました。
その浮世絵の影響を受けて生み出されたのが「印象派」の絵画です。
印象派の絵画は日本人好みだとよく言いますが、そのような経緯があるからこそなのですね。
☆ ☆ ☆
また、現在のフランスでは新たな「ジャポニスム」として、日本の漫画・アニメなどのサブカルチャーが(一部のマニアの間で)大流行なのは皆さんもご存じでしょう。
他にも日本の若者のファッションもフランスの若者に注目されています。
パリジェンヌが渋谷の109に憧れるというのは、パリに憧れる日本人の我々からすると不思議な感じがしますが本当の話。
皆さんもフランス語を身につけて、新たな日仏文化交流を生み出して行ってみてはどうでしょうか。
フランス語@神戸

そんなにスケールの大きな話をしなくても、神戸で生活をしているだけでも毎日さまざまなフランス語を目にすることができます。
たとえば道を歩いていると、英語のようで英語ではない、ちょっと変わった綴りや、àだとかéのような記号がついたアルファベットの看板を目にすることがありませんか?
そのお店がレストランやケーキ屋さんや美容院であれば、かなりの確率でその文字はフランス語です。
他にも雑貨店やマンションなどにもフランス語の名前はよく使われていますね。
神戸大学のお膝元、六甲の街並みを少し散歩するだけで10以上のフランス語の看板を見つけることができますよ。
☆ ☆ ☆
「でも、フランス語だとは分かっても、どう発音するのか分からない・・・」
そういう人も、大学のフランス語の授業で発音の規則を勉強すれば、すぐに街中のフランス語看板を読むことができるようになります!
だからといって国際貢献できるというような話ではないのですが、神戸ライフを満喫するためにもフランス語の勉強はおすすめです。