
神戸大学では、学部1年生の1年間、中国語・中国語・中国語・ロシア語の4言語から1つを選択し、その言語を週に2回、1年間かけて学修することになります。
中国語の授業がどのような雰囲気なのか、実際に授業を担当されている先生の文章を紹介しておきます。
また、後期にはSクラスという選抜クラスも開講されます。そちらの案内もこのページで紹介しています。
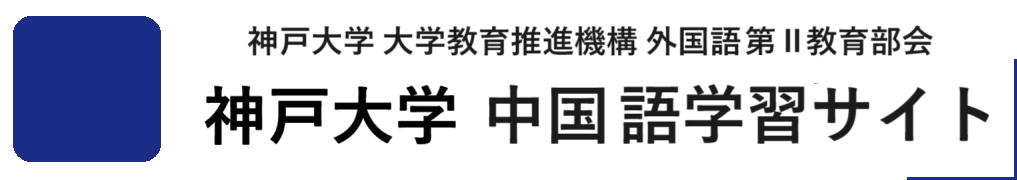
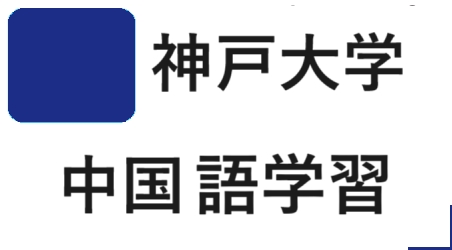
文字サイズ

神戸大学では、学部1年生の1年間、中国語・中国語・中国語・ロシア語の4言語から1つを選択し、その言語を週に2回、1年間かけて学修することになります。
中国語の授業がどのような雰囲気なのか、実際に授業を担当されている先生の文章を紹介しておきます。
また、後期にはSクラスという選抜クラスも開講されます。そちらの案内もこのページで紹介しています。
| 授業科目 | 授業内容 |
|---|---|
| 中国語初級A | (文法クラス:1年生第1Q~第4Q) 中国語による会話や読解の基礎となる基本的な文法の習得をめざします。文法における全体構造を理解し、異文化理解の基礎を固めることを目標とします。 |
| 中国語初級B | (実践クラス:1年生第1Q~第4Q) 主に文法を中心とするAの文法クラスと相互補完的に、発音・文法・語彙・文章表現などを総合的、多角的に学習し、多様なトレーニングを通して、読解力や表現力の向上をめざします。 |
| 中国語 初級SA・SB | (インテンシブ・クラス:1年生第3Q~第4Q) 1年次後期の第3・第4クォーターにおいて、「A3・B3」「A4・B4」の代わりに、「SA3・SB3」 「SA4・SB4」という名称のインテンシブ・クラスを選択することができます(通称「Sクラス 」)。ネイティブ教員と日本人教員が連携して授業を担当し、開講時間は全学部共通で火曜5限と木曜5限になります。通常クラスよりも少人数のクラスサイズなので、授業中は受講生と教師との対話が中心となります。 また、毎年Sクラス受講生の何名かは当該言語圏の大学への留学を目指し、そして実際に留学を叶えています。留学や語学研修に少しでも興味がある人は、積極的に受講することをお勧めします。(ただし保健学科を含む医学部ではSクラスの履修が認められていません。) Sクラスの履修案内に関しては、夏休み前までに、初級A・Bの各クラスにおいてチラシが配布されます。履修希望者は配布資料の説明をよく読んだ上で、各自申込手続きを行ってください。 |
| 授業科目 | 授業内容 |
|---|---|
| 中国語中級C | (2年生第1Q~第2Q) この科目は、選択科目となっています。1年次で履修・習得した外国語Ⅱをさらに深めたいという学生はこの中級Cクラスから始めてみましょう。なお、医学部(保健学科を含む)と海事科学部では、この2科目は開講されていません。 インテンシブ・クラスであるSクラスの延長として受講できる「中級C1・C2」クラスも設定されています。 |
| 高度教養科目 | 2年次後期からは、外国語第II教育部会が提供する「高度教養科目」として、「外国語セミナーA・B・C・D・E・F」を履修することができます。外国語第Ⅱ教育部会としては、この「高度教養科目」としての「外国語セミナー」も「アドバンスト科目」の一環として位置付けています。 まず「外国語セミナーA・B」が、2年次後期から履修可能な「高度教養科目」として位置付けられています。A・Bをともに履修することが望ましいですが、どちらか一方のみの履修も可能です。また、3年次以降になってから履修することも可能です。 「外国語セミナーC・D・E・F」は、A・Bよりもさらに高度な学習内容になります。A・Bを履修していない学生でも、担当教員により十分なレベルに達していると判断された場合には履修することが可能です。また、ベーシック科目のような積み上げ式ではなく、各クォーターで独立した内容なので、他の履修科目や留学などのスケジュールに合わせて履修選択することが可能です。 |
1年次の秋学期(第3・第4クォーター)に中国語Sクラスが開講されます。このクラスは、履修定員を20名に限定した上で学生の進度を一人一人見極めながら進んでいきます。中国語圏への長期留学を目指す学生や「将来中国語を自らの武器として使いたい学生」を対象に、中国語の基礎をしっかりと確立することが中国語Sクラスの目標です。
中国語Sクラスの一番のアピールポイントは、「言語学の知見にもとづいて中国語文法・音声を学べること」だと思います。中国語Sクラスの担当教員は初級SA3・SA4が日本人の髙橋康徳、初級 SB3・SB4が2023年秋から新たに着任する中国人教員ですが、どちらも言語学を専門分野としています。言語学を専門とする人間にとって、「世界の言語の中で中国語は珍しい特徴を持つ言語といえるか」、「中国語の形容詞は日本語や英語などと比べてどのような共通点と相違点があるのか」、「中国語で発音が難しい子音と母音はどれか。それらが発音される時、舌・顎・声帯がどういう状態になっているのか」などは全て重要な研究課題です。でも、これらはみなさんが外国語を勉強する上でぶつかる問題と重なりませんか?そこで中国語Sクラスでは、みなさんが持つ中国語の疑問に言語学的な観点から回答を与えながら授業を進めていきます(本当に難しい質問は教員の宿題になります)。もちろん中国語をマスターするため には中国の文学や歴史、文化なども広く学ぶ必要がありますが、発音の習得や文法の理解など初級段階において言語学の知見は大いに役立つと思っています。
初級SA3・SA4では、発音の基礎を確立させるために教科書本文の朗読を重視しています。中国語は子音・母音も少し難しいのですが、それに加えて「声調(声の高さ)」の区別があり、この3つの要素を同時にコントロールしないと正しい発音になりません。その上、中国語には「ピンイン」というローマ字の音声表記があり、これが分からないと1つの漢字も正確に読むことができません。初級SA3・SA4では、発音をしっかりマスターするため学生一人一人に教科書を朗読させる時間を確保しています。担当教員は、学生の発音を聞いた上で音声学的知見を生かしながら発音の修正を細かく行います。
初級 SB3・SB4では読解力の向上をメインの目標にしていますが、リスニングや会話練習も取り入れています。会話練習では、与えられたテーマについてクラスまたはグループ全員を相手に会話をしていきます。 同じテーマでも話す相手によって会話の進行や表現が異なりますので、臨機応変に対応しないと話が成立しません。この練習によって中国語での即会応力を鍛えるだけではなく、クラスメートの発話を参考にす ることで表現範囲を効率的に広げていくことができます。