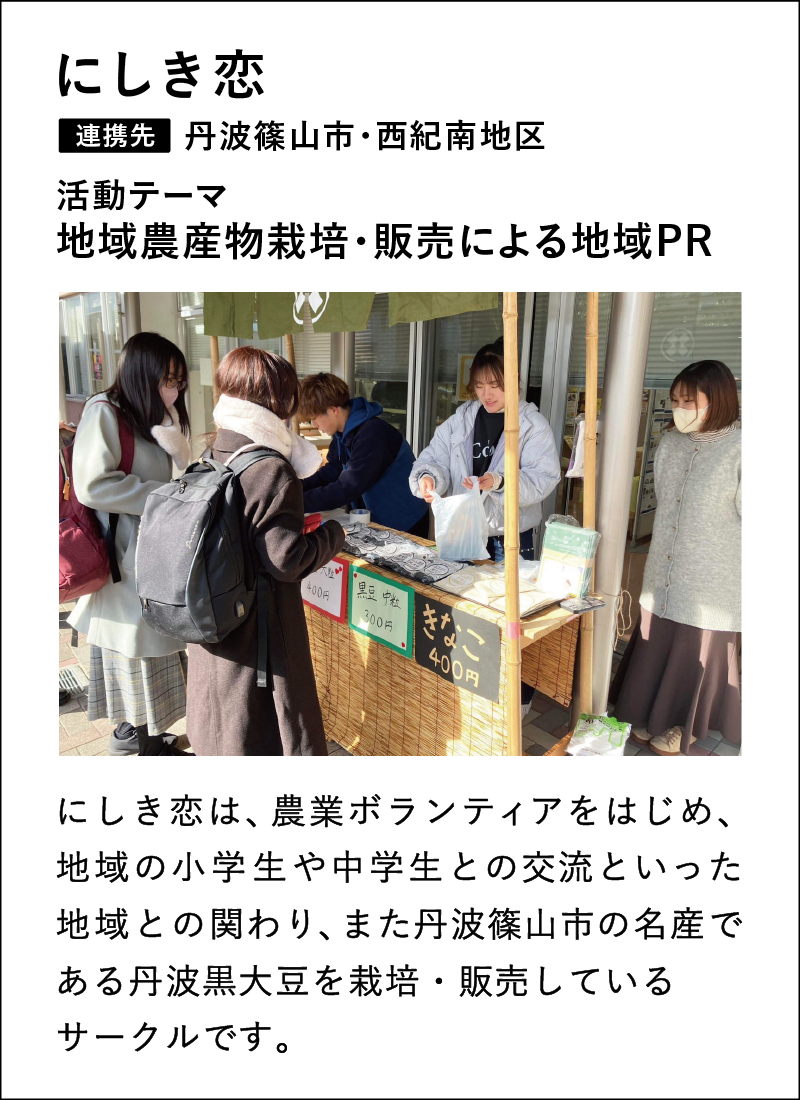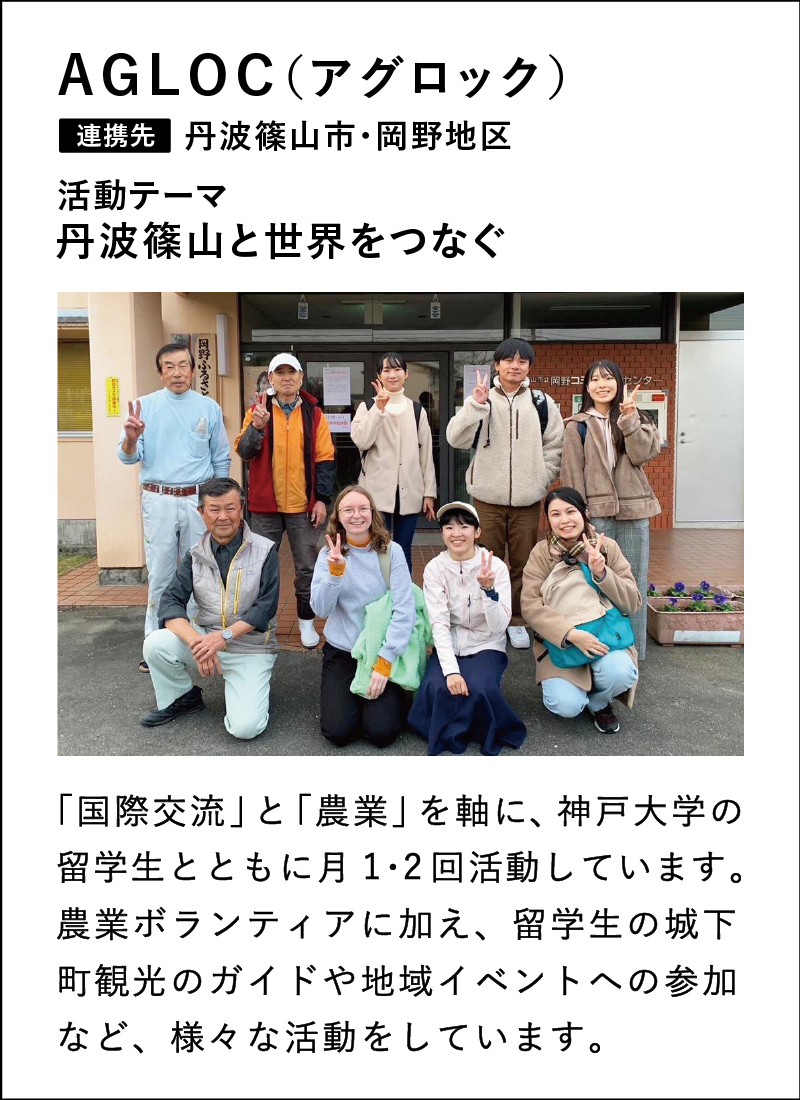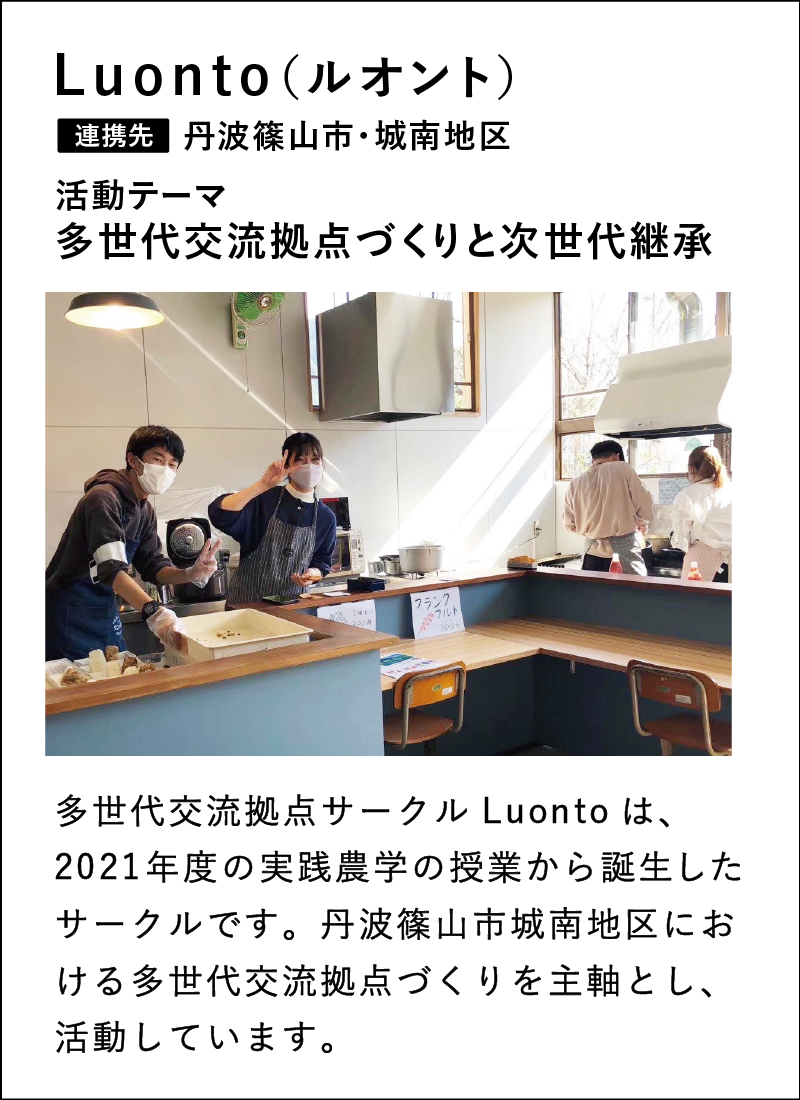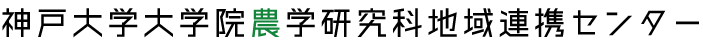ACTIVITY
地域交流活動
農学部と地域とのパートナーシップにより、懇話会、学習会、フォーラム・シンポジウムなどを開催し、知を共有して地域活動を推進します。行政施策の審議会や委員会などの委員、地域へのアドバイザー派遣の支援もおこないます。
フォーラム、研究会、セミナーの開催
地域連携研究会(A-Launch)
食と農の現場とつながり、活躍中の神戸大学の研究者や地域の実践家との対話を、ランチをとりながら楽しめるトークイベント。
より気軽に、幅広く、地域での実践活動や農学の先端研究・理論に出会える場として、2012年にスタートしました。
| 第23回 2024年 6月21日 |
「農と食と協同組合」 小寺收(地域連携センター) |
|---|---|
| 第22回 2023年 10月17日 |
「綿づくりから地域活性化ー綿から生まれたマヨネーズ!?ー」 濵田紗希(農学部4回生) |
| 第21回 2022年 6月21日 |
「これからの米作りと農村を担うのは誰だー山口県の集落営農を参考にー」 小川景司(農学研究科) |
| 第20回 2021年 12月22日 |
「日本茶の世界」 梅村崇(地域連携センター) |
| 第19回 2021年 3月9日 |
「ため池の現状と展望」 柴崎浩平(農学研究科) |
第18回 2020年 12月22日 |
「食と健康に関する機能性研究」 山下陽子(農学研究科 応用生命化学) |
地域連携ゼミ
地域連携に関わる若手の研究員中心の、自主的な研究会。1年に10回程度、開催しています。
バイオエコノミー研究会
ポスト化石燃料時代の農林水産業、工業、エネルギー利用、生態系など多様なトピックについて、セミナー形式で討論をおこなう集まりです。
| 第8回 2022年 7月20日 |
「持続可能な幕らしを支える共創型の小規模環境技術が果たす役割」 三橋弘宗氏(兵庫県立人と自然の博物館 主任研究員) |
|---|---|
| 第7回 2022年 1月28日 |
「カーボンニュートラル社会の実装に向けた微細藻類ユーグレナの利用」 豊川知華氏(株式会社ユーグレナ) |
| 第6回 2021年 11月30日 |
「脱炭素社会にむけたバイオエコノミーと農業ー再生可能エネルギー生産 との両立ー」 柴田大輔氏(京都大学エネルギー理工学研究所 特任教授) |
| 第5回 2020年 1月24日 |
「日本の森林管理とそれを担う林業事業体の組織マネジメント」 楢崎達也氏(FOREST MEDIA WORKS Inc. 代表) |
| 第4回 2019年 10月31日 |
「The Bioeconomy Approach: Constraints and Opportunities for Sustainable Development」 Dr. Nagothu Udaya Sekhar (NIBIO/ノルウェー・バイオエコノミー研究所) |
| 第3回 2019年 5月6日 |
「生物多様性ビジネスの最前線」 藤木庄五郎氏(株式会社バイオーム) |
| 第2回 2018年 11月6日 |
「地域がなぜエネルギー利用について考えるべきなのか〜西粟倉村ローカルベンチャーを事例として〜」 井筒耕平氏(株式会社sonraku 代表取締役) |
| 第1回 2018年 10月3日 |
「バイオエコノミーとは何か」 長野宇規(農学研究科 生産環境工学) |
農の学び場
Rural Learning Network
2012年に始まった農村地域の学習ネットワーク、通称:るーらん。1)地域の問題や取り組み実態の理解、2)先進的・革新的な取り組みや技術の共有、3)セクターと地域を越えたネットワークづくり、4)現場発の政策・事業・研究の形成の場となること、を目指しています。
| 第32回 2022年 12月14日 |
「地域の再生可能エネルギー 丹波篠山で何を始めよう?!」 荒木康孝氏(新宮エネルギー株式会社) |
|---|---|
| 第31回 2020年 1月29日 |
「草刈り人材の育成〜“畔師”グループをつくりませんか?〜」 木原奈穂子氏神戸大学大学院農学研究科 |
| 第30回 2019年 11月8日 |
山採りビジネス〜雑木を売って里山を守る方法とは?〜 西山雄太氏(リビングソイル研究所 代表) |
| 第29回 2019年 8月19日 |
「ため池の新たなエネルギー活用の可能性〜エネルギーの生み出し方と使い方とは?〜」 井筒耕平氏(株式会社sonraku 代表取締役) |
| 第28回 2019年 7月19日 |
「“田園回帰”の経済性:農村での生活が生み出す価値とは?」 立見淳哉氏(大阪市立大学経営学研究科) |
学生地域活動サポート
当センターでは、地域と連携した取り組みを進める学生団体に対し、情報提供、情報発信サポート、相談対応など、
活動の発展と充実に向けた支援を実施しています。