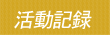2022年度授業内容
新型コロナウイルス感染症に伴う授業への制限が緩和され、今年度のゼミは、すべて対面で実施されました。
前期は、今年度のテーマである「福祉国家・共生社会論」についての文献を読み、各文献につき3、4人の担当者が論点をまとめました。ゼミでは、論点の発表と担当者が文献を読む中で疑問に思った点を共有し、1班6名程度のグループにわかれて議論を行います。その後、班の代表者が話し合いの結果を発表し、担当者が感想を述べました。最後に飯田先生からのコメントや論点についての掘り下げ、関連する思想家との相違点などに関する解説がありました。

後期では、前期で学んだ内容をふまえて各自テーマを決め、ゼミ論文を書きました。中間報告では、前期と同様の流れで担当者が挙げた論点をもとに議論を行います。論文の制作過程では、飯田先生が一人一人にアドバイスをしてくださいます。
以下は、今年度扱った文献のラインナップです。
・チャールズ・テイラー『マルチカルチュラリズム』
・G. エスピン・アンデルセン『福祉資本主義の三つの世界 比較福祉国家の理論と動熊』
・T.H. マーシャル/トム・ボットモア『シティズンシップと社会的階級』
・ジャスティン・ゲスト『新たなマイノリティの誕生』
・マルサス『人口論』
・ヘーゲル『歴史哲学講義(上)』
・ウィル・キムリッカ『多文化時代の市民権-マイノリティの権利と自由主義-』
・ジェレミー・ウォルドロン『ヘイトスピーチという危害』
・マーサ・C・ヌスバウム『女性と人間開発 潜在能力アプローチ』
・アイリス・マリオン・ヤング『正義と差異の政治』
・トニー・フィッツパトリック『自由と保障一ベーシック・インカム論争』
今年度のテーマは、少子高齢化時代における福祉の商品化や自己責任化、福祉格差の拡大、介護労働の男女分業、外国人労働力の増加、世代間対立など、今日の政治全体に及ぶ幅広い具体的論点を含んでいました。そのため、議論では様々な視点から意見が出され、新しい発見や気づきが多かったです。また、このゼミは学年関係なく自分の意見を出しやすい雰囲気なので、1年間を通して非常に有意義な時間を過ごすことができます。
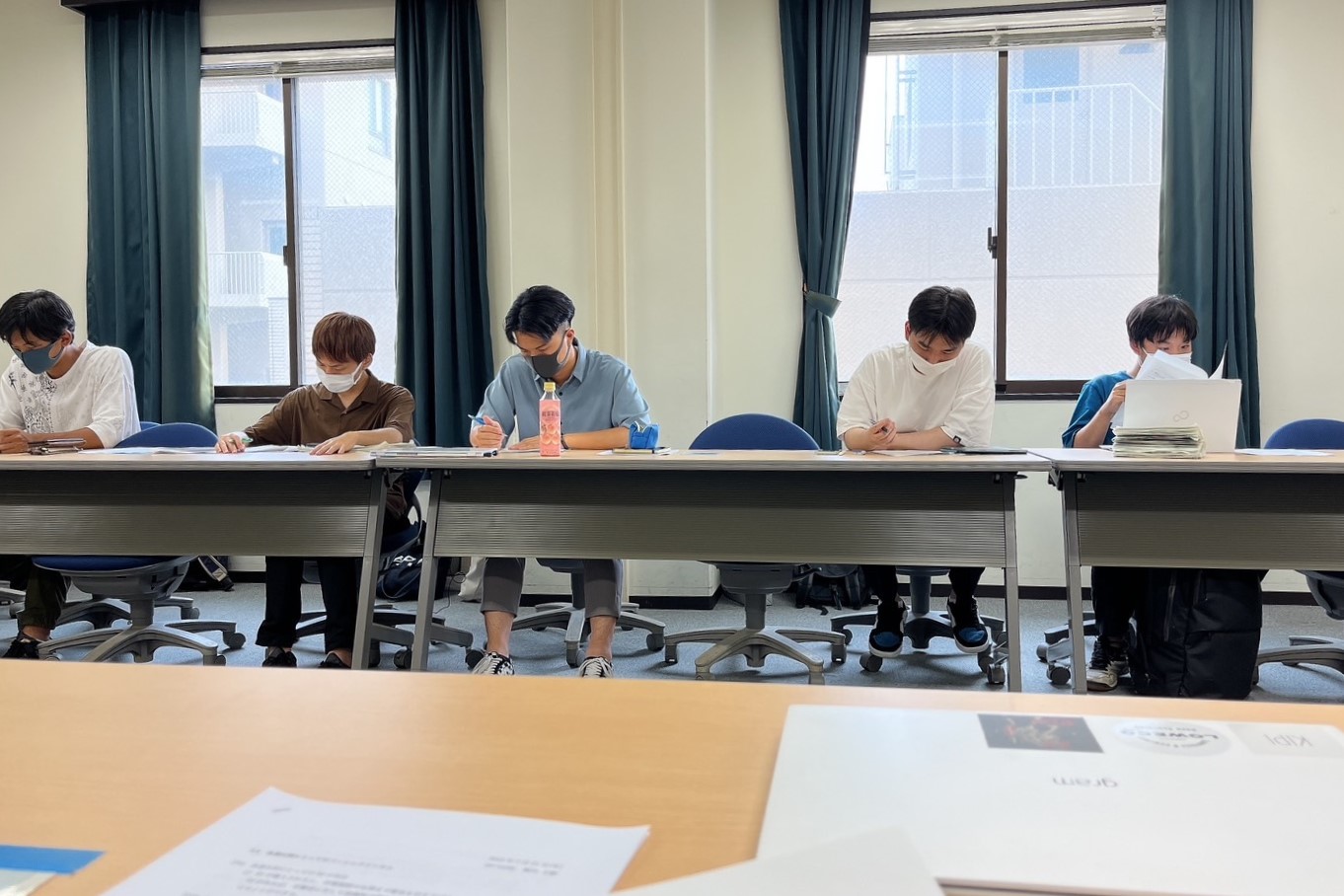

飯田ゼミは、以上のように、政治学に関する文献を読み、議論を通して理解を深め、論文を書くという活動を和気あいあいと行っているゼミです。
新型コロナウイルス感染症に伴う授業への制限が緩和され、今年度のゼミは、すべて対面で実施されました。
前期は、今年度のテーマである「福祉国家・共生社会論」についての文献を読み、各文献につき3、4人の担当者が論点をまとめました。ゼミでは、論点の発表と担当者が文献を読む中で疑問に思った点を共有し、1班6名程度のグループにわかれて議論を行います。その後、班の代表者が話し合いの結果を発表し、担当者が感想を述べました。最後に飯田先生からのコメントや論点についての掘り下げ、関連する思想家との相違点などに関する解説がありました。

後期では、前期で学んだ内容をふまえて各自テーマを決め、ゼミ論文を書きました。中間報告では、前期と同様の流れで担当者が挙げた論点をもとに議論を行います。論文の制作過程では、飯田先生が一人一人にアドバイスをしてくださいます。
以下は、今年度扱った文献のラインナップです。
・チャールズ・テイラー『マルチカルチュラリズム』
・G. エスピン・アンデルセン『福祉資本主義の三つの世界 比較福祉国家の理論と動熊』
・T.H. マーシャル/トム・ボットモア『シティズンシップと社会的階級』
・ジャスティン・ゲスト『新たなマイノリティの誕生』
・マルサス『人口論』
・ヘーゲル『歴史哲学講義(上)』
・ウィル・キムリッカ『多文化時代の市民権-マイノリティの権利と自由主義-』
・ジェレミー・ウォルドロン『ヘイトスピーチという危害』
・マーサ・C・ヌスバウム『女性と人間開発 潜在能力アプローチ』
・アイリス・マリオン・ヤング『正義と差異の政治』
・トニー・フィッツパトリック『自由と保障一ベーシック・インカム論争』
今年度のテーマは、少子高齢化時代における福祉の商品化や自己責任化、福祉格差の拡大、介護労働の男女分業、外国人労働力の増加、世代間対立など、今日の政治全体に及ぶ幅広い具体的論点を含んでいました。そのため、議論では様々な視点から意見が出され、新しい発見や気づきが多かったです。また、このゼミは学年関係なく自分の意見を出しやすい雰囲気なので、1年間を通して非常に有意義な時間を過ごすことができます。
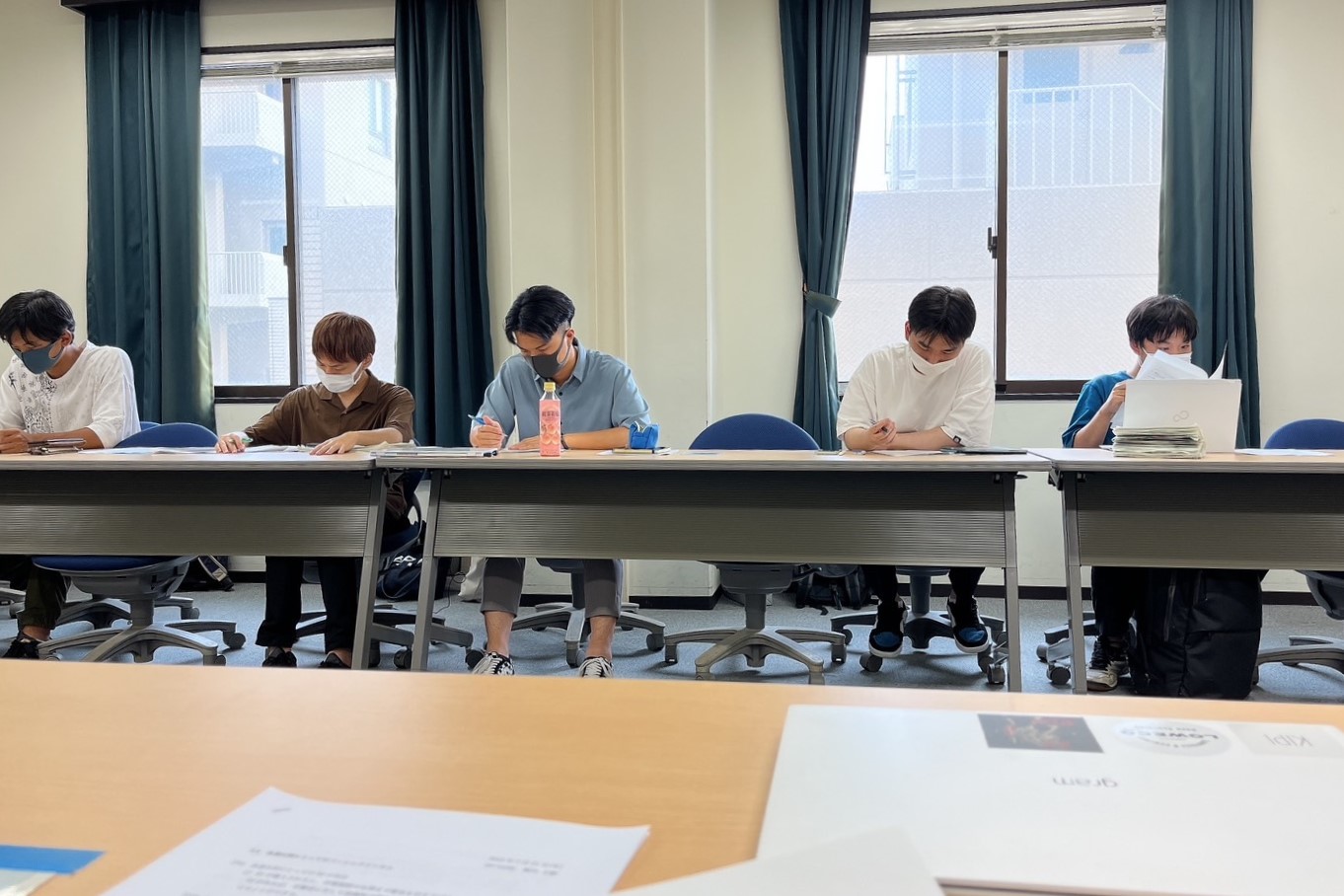

飯田ゼミは、以上のように、政治学に関する文献を読み、議論を通して理解を深め、論文を書くという活動を和気あいあいと行っているゼミです。