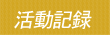今年は、世界的にコロナウイルスが蔓延したことによって、ほとんどの授業をオンライン行いました。しかし、後期の最後の授業は対面で行うことが出来ました。
ちなみに最後の授業はなんと飯田先生がケーキを差し入れてくださいました!!
前期では、今年度のテーマである「民主主義」についての文献を読み、各文献につき3、4人が担当して論点をまとめました。ゼミでは担当者が論点を述べ、文献を読むなかで浮かんだ疑問点や感想をあげます。それについて3グループ(各グループにつき担当者が1人つく形)にわかれ全員で議論しました。担当者は各グループの結論を受け、疑問点について改めて考えを述べます。最後に飯田先生からのコメントや論点についての掘り下げ、関連する思想家とどの点が違うのかや重要なキーワードなどについて解説していただいています。
後期では、前期で学んだ内容をふまえ、各自テーマを決め、それについて論文を書きます。
.jpg)
ゼミの特徴として、議論を3回生と4回生にわかれることなく行うことや、他のゼミと比べゼミ時間外で時間を拘束されることが少ないということがあります。そのため、他学年の学生と議論する機会や、就活・勉強・部活と両立しやすいということがあります。実は今回のゼミは、対面では2度目ですが、オンラインでのゼミを通して、最初はなかなか発言出来なかった3年生もしっかりと自分の意見を述べることができるようになりました。
一回の授業で1つの教材というペースで進めていきました。前期はじっくりと教材を読み込む癖がつくので、文献を読む習慣がないゼミ生でも、意見を討論することができるようになります。
議論は、先輩と後輩という関係であっても、白熱してしまうこともある、一方で、論文の難解さに頭を抱えながらも、何とか具体的な内容として理解しようと皆で協力して進めて行きます。
.jpg)
こちらは、今年度扱った文献のラインナップです。
・ シュンペーター『資本主義・社会主義・民主主義』
・ ロバート・A・ダール『統治するのはだれか』
・ C・B・マクファーソン『自由民主主義は生き残れるか』
・ トグウィル『アメリカのデモクラシー』
・ マイケル・J・サンデル『民主制の不満 公共哲学を求めるアメリカ』
・ ルソー『社会契約論』
・ ノーム・チョムスキー『アメリカを選挙せよ』
・ ユルゲン・ハーバーマス『事実性と妥当性』
・ 田村哲樹『熟議の理由』
・ シュミッター、オドンネル『民主化の比較政治学』
・ サミュエル・P・ハンチントン『民主主義の統治能力』
・ レイプハルト『民主主義対民主主義』
・ トマス・ポッゲ『なぜ遠くの貧しい人への義務があるのか』
・ ヤン=ヴェルナー・ミュラー『ポピュリズムとは何か』
.jpg)
.jpg)
飯田ゼミは、以上のように、政治学に関する文献を読み、議論を通して理解を深め、論文を書くという活動を和気あいあいと行っているゼミです。
.jpg)